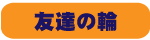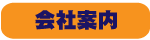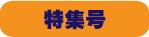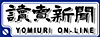友達の輪699号(2025年2月2日発行)
コーラス四季の会 竹下 正光さんへ
【本紙】 市民合唱などコーラスはいつごろからやられているのですか?
【竹下】(敬称略) かれこれ14年くらいになります。最初は「歌声ゴンドラ」への参加から始まり、それから市民合唱に誘われました。私がというより、妻が高校時代にコーラス部だったのです。市民合唱を主宰されている芝さんと小学校のPTAで繋がったという感じですね。もう30年來の付き合いになります。芝さんはピアノ教室の先生で、ゴンドラという歌声喫茶を始めるところから手伝ってきました。最初は喫茶店「アミ」で開催していました。MC(芝さん)、伴奏者、リードボーカル、あとは手伝いなどをやってくれるスタッフ数人です。芝さんが選曲された歌謡曲や童謡・唱歌・フォークソングなどをみんなで歌っていました。当然リクエストもあります。今もゴンドラは「プラス」(商工会直営)で続けています。ほかに若返り歌声クラブという公民館活動にも参加しています。私はそれらで使う歌集などの編集を手伝いました。
【本紙】 竹下さんは今でも全部に参加されているのですか?四季の会の代表の渡邊省三さんより譜面を作られているとお聞きしました。
音取り音源作成
【竹下】 ゴンドラは幸手商店街にあるプラスという会場で、今でも月に2回歌声喫茶を開催していますが、私は歌っていません。会場設営と歌集の編集を手伝うだけです。今は西公民館での市民合唱と南公民館でのコーラス四季に参加しています。ただ単に歌うだけではなく、何らかの役割を見つけて歌うほうが性に合っています。市民合唱ではパート別に歌うという分担があります。私のバスパートはメロディと違いますから、つられないよう暗譜しないといけません。残念ながら歌は下手だねと言われています。音取りCDがないとついていけません。当初市販の音取りCDを購入して自習しましたが、次年度から自分で作ろうとプリントミュージックというソフトを購入しました。ソプラノやアルトなど各パートの譜面をパソコンにインプットするだけで音源が出力されるソフトです。市民合唱に入った翌年からやっていますので14年位になります。ピアノやギターを弾ける人は自分で音取りできますが、合唱する皆さんが楽器を奏でるわけではありません。私はパソコンソフトが頼りです。ついでに他のパートの音取りCDを必要とする仲間の分も作っています。難しい楽曲ではバス仲間を誘って練習したこともありました。パソコンではそういう楽しみ方もできます。コーラス四季ではメインが二部合唱でしたが、四部合唱も多くなってきましたので、音取りCDを使って自習を楽しむ人も出てきました。24年第5回コンサートでは18曲歌いましたが、各パート全曲音取りCDを作成しました。またコンサートのために毎週火曜日、歩け歩けクラブの四季の仲間4,5人で、プロジェクタに楽譜を映して自主練習を続けました。第5回では編曲された楽譜の作成にも携わり、充実したコンサートになりました。
【本紙】 再来年にコーラス四季は20周年だそうですね。
コーラスを掘り下げ
【竹下】 そうですね。そのために課題曲の音取りの打ち込みに取り組んでいます。決まった曲はインプットして自習仲間で練習しています。さらに20周年コンサートに向けてコーラスの楽しみ方を掘り下げています。私は行動規範として、1.全体像をつかめ!、2.目標管理を遂行する!、3.原理原則をつかむ!、4.PDCAをまわす!、5.条件整備を先行する!を掲げています。三位思考法では「結果=目標×(心×体×技)×気」という方程式に当てはまる用語を捜し出して図や表にしています。音楽には原理原則がたくさんあります。たとえば音取りでは音階(ドレミ)、音程(度数や半音)、音符(4部や休符)、和音ではキー(#や♭)、リズム(4/4や3/4)、テンポ(♩=60や♩=100)が一体とならないとハーモニーになりません。何事も三位一体なのです。あたり前なことは分かっていても出来るわけではありませんが。皆さんから音楽は、理屈ではなく感覚で楽しむものだと煙たがられますね。私は合唱を始めてから14年間、先生たちが指導される言葉を整合し続け、ようやく全体像にまとまりつつあります。24年2月から市民合唱の小川先生に、ソロで歌う声楽講座を月1回受講しました。そのとき十年前から先生が、機会あるごとに言われていた舌や喉のストレッチ方法を思い出して、自習したところ声が響くようになったのです。毎朝、舌苔ブラシを喉に近づけると「オェッ」となり、喉が広がります。また舌を噛んで「ウッウッ」と喉を鳴らすことで喉のストレッチになります。さらに濡れタオルで舌を引っ張って歌い、喉頭部をほぐします。その成果が出て、24年9月の発表会での出来映えを、仲間から褒めてもらえました。原理原則は意識しながら体感するまでやり続けることが大切です。口腔のストレッチは毎日続けていますし、機会あるごと仲間にもすすめています。
【本紙】 先生から教えてもらったことを自分で分析した結果ですね。コーラスを分析しようと思ったのは?
三位思考法を発見
【竹下】 私の哲学のようなものです。20代のころから三位思考法での掘り下げに取り組んできました。そして仲間たちに持論を話すのが好きだったですね。早稲田の哲学科に通っていた学生と旅先で話しあったことは懐かしい思い出です。その頃に三位思考法(さんみしこうほう)というものを発見して、それからずっと仕事関係に活かしてきました。40歳ころ会社の月刊誌に連載しました。退職後の今はコーラスをはじめ、自分が体験した分野はなんでも掘り下げています。三位思考法は私の造語で元からあるものではありません。三位思考法についての本を出そうとしたこともあるのですが、上手く説明できませんでした。技術的な図や表ですから、言葉や文章で説明するのが難しく、私の文章力ではわかりやすく書くことができませんでした。昔、高校の先輩にコンサルティングを勧められたことがあるのですが、そっちの才能もなかったのでやることはなかったですね。ただ今なら、昔よりも自分の考え方が整理できていますし、伝える準備は整いつつあると思っています。
【本紙】 これを読んで三位思考法に興味を持った方が連絡をしても大丈夫ですか?
興味をもったら
【竹下】問題ありません。むしろこちらから話をしたいくらいです。80歳を越え、自分の身に何があるか分かりませんし。自分しかやっていないことは、世の中に出さないと心残りです。
【本紙】 活かせるといいですね。ご趣味はありますか?
【竹下】 2年前車の事故をやってしまいまして、それを機に自転車を重用するようになりました。自転車は好きで、南公民館・西公民館・中央公民館への移動に使っています。20代のころ横浜から姫路まで、姫路から長崎まで、青森から松戸まで、稚内から函館まで4回に分けて自転車旅をしたこともあります。今では幸手の御幸湖と江戸川土手の周辺で、季節を味わいながらサイクリングしています。健康的にも自転車はいいと感じています。
【本紙】 では、お友達をご紹介ください。
【竹下】 市民合唱仲間の中江卓二さんを紹介します。
【本紙】 ありがとうございました。益々のご活躍をお祈りします。(竹下さんは90年近い歴史がある長崎県立長崎工業高校が母校だそうで、今でも同窓会の会報誌「元気しとっと!」の編集長をなさっているそうです。)